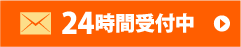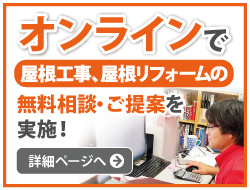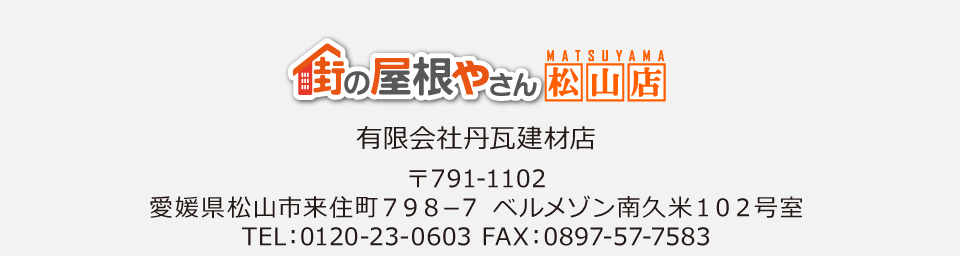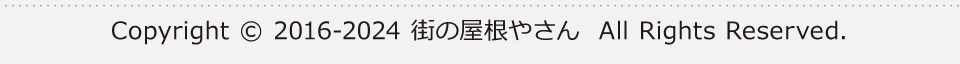愛媛県久万高原で見た日本古来の屋根技法の一つである茅葺き屋根
日本古来の伝統的な屋根である『茅葺き屋根』の魅力を紹介します。
私が今回行って来た、愛媛県久万高原にある『ふるさと旅行村』の写真を添えて説明します。

久万高原町『ふるさと旅行村』にある茅葺き屋根の喫茶店の写真です。
茅葺き屋根の歴史は古く北海道から沖縄まで(日本全国)、住宅に限らず社寺仏閣などの色んな建造物に用いられてきました。
古代の住宅形式を伝えるといわれている世界文化遺産にも登録された岐阜県にある白川郷や富山県にある五箇山の集落も茅葺き屋根になります。
近くで見ると物凄く重厚感がありどっしりとした感覚を受けました。
そこにいるだけで心が和み癒してくれる、日本古来の伝統的な建築物は本当に素晴らしいですね。
先人の知恵が生み出した何層にも茅(かや)が重なり合った屋根

茅(かや)という草は実は存在していないもので、ススキ・チガヤといったイネ科に属する多年草を総称して『茅』呼ばれているんです。中には藁葺き・草葺きと区別して言う場合もあります。
茅の形状としては茎(くき)の部分がストローの様な形状になっているため、そこに空気層ができ何層にも重なり合う事で強い断熱効果と保温性・防水性が生まれ冬場の寒さや雨風を凌ぐ事ができていたんですね。
先人の方達の知恵や技術が光るものが見れてとても素晴らしかったです。
この茅葺き屋根は日本独自のものではなく、イギリス・ドイツや北欧(北ヨーロッパ)といった世界各地でも多く用いられてきた原初的な屋根とされています。
日本でも、縄文時代には茅葺き屋根の住居が作られ、そこで人々が生活していたのではないかと考えられています。
昔の人達の『技術』が現代に残り今に受け継がれていく

現在の建築物の屋根の作りもこのように母屋(もや)の上に垂木が乗り、その上から屋根材を葺いていくといった建築構造は昔も今も変わらず、現代に受け継がれているのはとても感慨深いもの感じさせるものでした。
今ではたくさんの便利な建築工具があり家を建てるのも物凄く早くなりましたが、昔は石などを加工して作った打製石器を使い屋根の原料となる草木を伐採してそれを屋根材として使い茅葺き屋根の家を築いていました。
『茅葺き』はまさに、日本の古来から受け継がれてきた伝統的な技法と言えるのではないでしょうか。
ちなみに茅葺き屋根の葺き替え時期は場所やそこの環境にもよりますが大体15~20年と言われていて、屋根全体を葺き替えする場合がほとんどなんですが、棟(むね)の部分に関しては定期的な補修が必要とされています。
茅葺き屋根であっても棟の部分には耐久性を高めるためにヨシ(イネ科の多年草)を使う場合があり、屋根全体をヨシだけで葺いた場合は40年持つとも言われています。
茅葺き屋根の軒先部分は切り揃える方が見た目は美しくなるのですが、切り揃えない方が水はけが良くなるとも言われています。
また水切り性を高めるためや軒先の直線を美しくする為に、軒先
部分にのみ細く硬い麻の茎(あさのくき)や苧殻(カラムシの茎)を用いる事もあるようです。

喫茶店に入り天井裏を見上げてみると、天井が表わしという技法が使われており垂木と母屋(もや)を結ぶ、縄の結び方が『いちごがけ』という特殊な技法が用いられており途中で縄を切らずに一本の縄で縛っていくことで、何年か経ってから途中で縄が切れたとしても他の縄がその部分を補うような工夫が施されていました。
屋根裏には大きな空間があり色んなものを保管したりできる工夫がされていました。
昔の人達は収穫したお米や小麦などの穀物類を冷暗所の代わりとしてこのスペースを使っていたのかなと勝手に想像を膨らましておりました。

日本古来の風情や歴史を感じさせてくれる『茅葺き屋根』はとても魅力的でした。
現代の表現で言うならば、環境や循環を意識し配慮したとても『エコロジーな住宅』と言えるのではないでしょうか?
最後まで読んで頂きありがとうございます。
他のコラムも読んで頂けると幸いです。
8時~18時まで受付中!
0120-23-0603